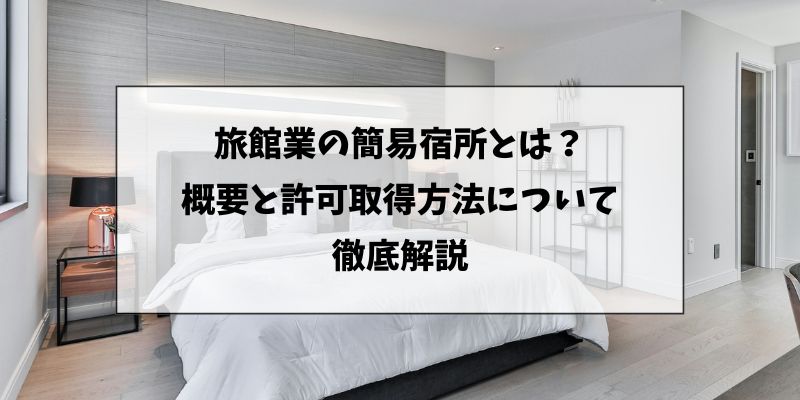民泊の運営を始める際にまず考えるのは、民泊新法(住宅宿泊事業法)、簡易宿所(旅館業法)、特区民泊(国家戦略特別区域法)といった3つのどの制度に則って始めるかを決めなければいけません。
今回は民泊の制度の中でも営業日数の縛りがなく、売上の最大化を狙える簡易宿所(旅館業法)について仮設していきます。
簡易宿所営業とは?
簡易宿所営業とは旅館業の種別のひとつです。
旅館業とは「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されており、「宿泊」とは「寝具を使用して施設を利用すること」とされています。
簡易宿所営業は、「宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」とされています。
参照:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130600.html
旅館業の種別
旅館業の種別には簡易宿所営業の他に、旅館・ホテル営業と下宿営業があります。
簡易宿所営業…宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のもの。
旅館・ホテル営業…施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のもの。
下宿営業…施設を設け、1月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて人を宿泊させる営業。
参照:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000111008.html
旅館業は許可が必要
簡易宿所営業を行うためには、都道府県知事(保健所設置市又は特別区にあっては、市長又は区長)の許可が必要となっており、許可を受けるためには旅館業法施行令で定める構造設備基準や都道府県の条例で定める衛生基準に従ってなければなりません。
許可なし営業は旅館業法違反
旅館業法の許可を得ずに旅館業を行った場合は、旅館業法違反となり重たい罰則があります。
旅館業法第10条「6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」とされています。
平成30年住宅宿泊事業法が施行
住宅の一部や全部を活用した民泊サービスの普及に伴い、平成30年6月15日より、新たな民泊サービスの枠組みを定めた住宅宿泊事業法が施行されました。
住宅宿泊事業法は届出で事業開始ができるため、旅館業法の許可に比べ事業を開始しやすくなりました。一方で180日間の営業可能上限があるため、180日を超えた営業を行いたい場合は旅館業法の許可が必要となります。
簡易宿所営業の要件
簡易宿所営業を行うための主な要件をまとめました。許可取得がスムーズに行えるようにチェックしておきましょう。
簡易宿所の構造設備基準
客室の延床面積は、33平方メートル(宿泊者の数を10人未満とする場合には、3.3平方メートルに当該宿泊者の数を乗じて得た面積)以上であること。
階層式寝台を有する場合には、上段と下段の間隔は、おおむね1メートル以上であること。
適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること。
宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
適当な数の便所を有すること。
その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること。
用途地域制限がある
用途地域とは、都市を住宅地、商業地、工業地などいくつかの種類に区分し定めたものです。
簡易宿所営業は、原則として第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、田園住居地域、工業専用地域での営業ができません。
用途地域は各自治体で提供しているシステムか建築基準法担当窓口で確認ができます。
施設との賃貸契約内容や管理規約
簡易宿所は所有物件でなく、賃貸マンション等でも営業は可能です。
しかし、賃貸借契約の中で転貸が可能であることや民泊サービス使用ができる旨が記載されている必要があります。
また保有物件でも分譲マンション等の場合は、マンション管理規約に同様に使用許可が記載されているかの確認が必要です。