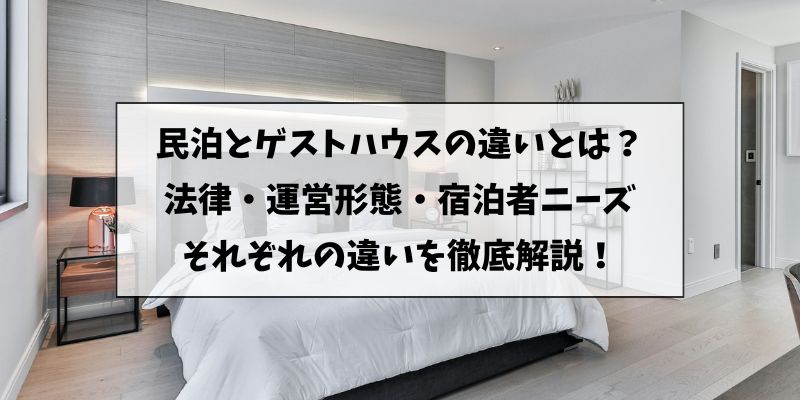「民泊」も「ゲストハウス」も宿泊料を受けて人を宿泊させる宿泊事業です。しかし、双方には法律・運営・宿泊者目線による印象に違いがあります。
双方の違いを正しく理解して自分に合う事業形態を選びましょう。
民泊とゲストハウスの定義
民泊とゲストハウスに明確な定義は存在しませんが、定義するとすると下記になります。
- 民泊:住宅(戸建住宅やマンションなど)の全部または一部を、旅行者などに宿泊サービスとして提供すること
- ゲストハウス:宿泊場所を多数人で共用する宿泊施設
広義には民泊の運営形態の一つにゲストハウスがあるとも考えることができます。
最初に用語を整理します。民泊とは住宅を活用し、年間180日以内で宿泊サービスを提供するビジネスです。根拠法は住宅宿泊事業法、いわゆる「民泊新法」で、届出制が採用されています。
一方のゲストハウスは旅館業法上の「簡易宿泊所」に分類され、365日営業が可能です。ドミトリー形式のベッド販売を組み合わせることで、客室あたりの売上を引き上げやすい点が特徴です。
民泊とゲストハウスの法律上の違い
民泊とゲストハウスの法律で区分するなら、民泊は民泊新法(住宅宿泊事業法)、ゲストハウスは旅館業法(簡易宿泊所)として運営されます。
民泊新法(住宅宿泊事業法)
2018年に施行された民泊新法は、空き家問題の解決とインバウンド需要の受け皿拡充を目的に制定されました。届出はインターネットで完結(一部エリアでは対面の場合あり)し、家主居住型・家主不在型のいずれも可能ですが、「年間営業日数は最大180日」と明確に制限されています。
加えて自治体ごとに独自ルールも設けられています。
旅館業法(簡易宿泊所)
旅館業法(簡易宿泊所)では、「年間営業日数は最大180日」の制限がなくなり、365日営業が可能になります。民泊新法ではインターネットで完結(一部エリアでは対面の場合あり)できた届出は、許可制となり申請難易度が上がります。
民泊新法(住宅宿泊事業法)と旅館業法(簡易宿泊所)の比較表
民泊とゲストハウスの違いを理解する上で押さえておきたい民泊新法(住宅宿泊事業法)、と旅館業法(簡易宿泊所)の違いを表でまとめました。
| 旅館業法 (簡易宿所) |
国家戦略特区法 (特区民泊に係る部分) |
住宅宿泊事業法 | |
|---|---|---|---|
| 所管省庁 | 厚生労働省 | 内閣府 (厚生労働省) |
国土交通省 厚生労働省 観光庁 |
| 許認可等 | 許可 | 認定 | 届出 |
| 住専地域での営業 | 不可 | 可能 (認定を行う自治体ごとに、制限している場合あり) |
可能 条例により制限されている場合あり |
| 営業日数の制限 | 制限なし | 2泊3日以上の滞在が条件 (下限日数は条例により定めるが、年間営業日数の上限は設けていない) |
年間提供日数180日以内 (条例で実施期間の制限が可能) |
| 宿泊者名簿の作成・保存義務 | あり | あり | あり |
| 玄関帳場の設置義務 (構造基準) |
なし | なし | なし |
| 最低床面積、最低床面積 (3.3㎡/人)の確保 |
最低床面積あり (33㎡。ただし、宿泊者数10人未満の場合は、3.3㎡/人) |
原則25㎡以上/室 | 最低床面積あり (3.3㎡/人) |
| 衛生措置 | 換気、採光、照明、防湿、清潔等の措置 | 換気、採光、照明、防湿、清潔等の措置、使用の開始時に清潔な居室の提供 | 換気、除湿、清潔等の措置、定期的な清掃等 |
| 非常用照明等の安全確保の措置義務 | あり | あり(6泊7日以上の滞在期間の施設の場合は不要) | あり(家主同居で宿泊室の面積が小さい場合は不要) |
| 消防用設備等の設置 | あり | あり | あり(家主同居で宿泊室の面積が小さい場合は不要) |
| 近隣住民とのトラブル防止措置 | 不要 | 必要 (近隣住民への適切な説明、苦情及び問合せに適切に対応するための体制及び周知方法、その連絡先の確保) |
必要 (宿泊者への説明義務、苦情対応の義務) |
| 不在時の管理業者への委託業務 | なし | 規定なし | 規定あり |
参照:https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/overview/minpaku/index.html
民泊とゲストハウスの事業開始難易度の違い
上記の法律上の違いで区分するとすれば事業開始の難易度は民泊の方が容易で、ゲストハウスの方が難しくなります。
初期費用も大きく変わってくる
民泊運営はマンションの一室から開業が可能で、一般的な賃貸マンションは民泊新法(住宅宿泊事業法)の要件を満たしている場合が多くあります。
そのため、初期費用としては内装や家具等の準備のみでよかったりします。
一方でゲストハウスは、施設自体を旅館業法(簡易宿泊所)に合わせた大幅改修が必要な場合があり、コストが嵩みます。
許可申請の難易度
インターネットでの届出(一部エリアでは対面の場合あり)で良い民泊に対して、旅館業法(簡易宿泊所)は許可制となり難易度が上がります。
その分、代行費用にも違いがあり、民泊申請代行は15~20万円程度で可能ですが、旅館業法の申請は25〜40万円程度と難易度が高い分費用も高くなります。
営業できる地域の違い
都市計画において土地は住居、商業、工業などの用途ごとに区分されています。
13種ある用途地域のうち、民泊新法では工業専用地域を除く12種の用途地域で営業が可能です。一方で旅館業法では6種の用途地域でのみ営業が可能です。
特に民泊新法では住居専用地域で営業が可能な点が大きな違いで、戸建て住宅やマンション・アパートなど営業可能な物件が多くあります。
民泊とゲストハウスのニーズの違い
民泊とゲストハウスでは宿泊者ニーズも大きく異なってきます。
民泊の宿泊者ニーズ
民泊宿泊者のニーズとしてはコスパよくリッチな宿泊施設を利用したい、家族や友人グループで1つの宿泊施設を利用したい、宿泊施設内でBBQや花火などのイベントを行いたい、などがあります。
すなわちホテルより安い料金でホテルのような快適感がほしかったり、グループでプライベート空間を楽しみたいといったニーズになります。
ゲストハウスの宿泊者ニーズ
ゲストハウスは1つの施設を共用利用するため、宿泊費を低く抑えることが大きな特徴です。
また1人旅で宿泊所での交流を重視したい、外国の方と異文化交流をしたいといったニーズも満たしてくれます。
さらに現地の知識が豊富なホストが常駐しているため、現地でしか得られないような特別な情報を入手できたりもします。
民泊もゲストハウスも事業成功の秘訣は同じ
民泊もゲストハウスも事業成功の秘訣には共通部分があります。
顧客満足度を上げる
宿泊事業はいかに新規を獲得し、一度利用した人にリピート利用してもらうことができるかが重要です。
新規利用者もリピート利用者も獲得のためには顧客満足度を上げ、OTA(オンライン旅行サービス)やGoogleマップでの高評価・良口コミを増やせられるかが重要です。
高評価・良口コミにおいて重要なことはミスマッチを防ぐことです。思ったより汚かった、あるはずの設備がなかった、といった状況は宿泊費がいくらであろうが低評価の可能性が上がってしまいます。
要するにOTAやHPに的確な情報を明記し、真実の範囲内で見栄えを良くすることが重要です。
運営代行会社は集客もプロ
民泊運営経験が乏しい場合に自前で集客を頑張ろうとしても限界があります。そこは集客コストと割り切って運営代行会社へ委託するのもひとつの方法です。
運営代行会社の豊富な管理実績・経験から宿泊者が求めるニーズを把握しており、そのニーズを満たすサービス設計も熟知しています。
また、OTAやHPで掲載すべき情報の整理やプロのカメラマンによる写真撮影など、宿泊したくなる掲載を代行してくれます。