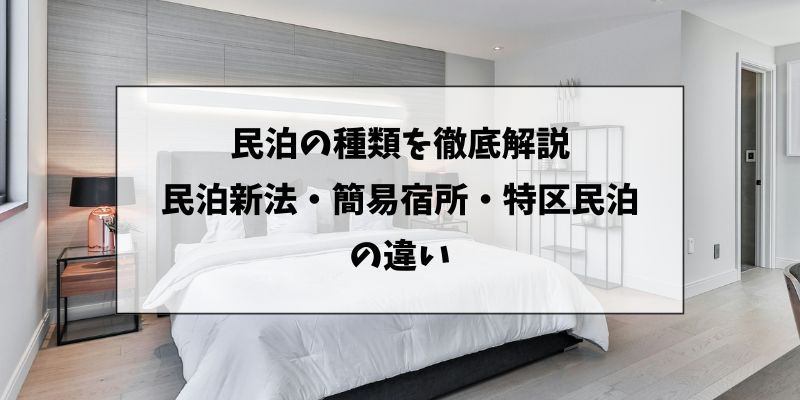インバウンドニーズの増加に伴い、これから民泊事業を展開したい個人・企業も増加しています。しかし、民泊事業は法規制に則った運営が必要であるため、最低限の知識の習得が必要です。
今回は民泊の種類に関して、民泊新法(住宅宿泊事業法)、簡易宿所(旅館業法)、特区民泊(国家戦略特別区域法)の3つの法律から解説します。どの法律が自分の運営スタイルに合っているか確認していきましょう。
民泊の3つの種類
民泊を種類分けするとすれば、民泊新法(住宅宿泊事業法)、簡易宿所(旅館業法)、特区民泊(国家戦略特別区域法)の3つに分けることができます。
民泊新法(住宅宿泊事業法)
民泊新法(住宅宿泊事業法)に則って民泊運営をする場合は、都道府県知事や保健所設置市の長等への届出が必要になります。
住専地域での営業が可能(一部地域では条例により制限)ですが、年間の営業上限日数が180日(泊)に定められています。
家主居住型で運営をする場合は、「衛生確保措置、宿泊者に対する騒音防止のための説明、近隣からの苦情への対応、宿泊者名簿の作成・備付け、標識の掲示等」の適正に事業を遂行するための措置が義務付けられています。
家主不在型で運営をする場合は、住宅宿泊管理業務を管理業者への委託しなければいけません。
簡易宿所(旅館業法)
旅館業法の簡易宿所営業に則って民泊運営をする場合は、各都道府県の保健所に申請を出し、営業許可を得なければいけません。
許可取得が営業するための条件となるため、届出の民泊新法よりはハードルが高くなるものの、営業日数の制限がなく365日営業が可能です。
ただし、住専地域での営業が不可となり、営業できるのは用途地域の中の第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域となります。
客室の合計延べ床面積も「33㎡」といった条件もあります。
特区民泊(国家戦略特別区域法)
特区民泊は法的には「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業」とされ、外国人旅行者の長期滞在を促す目的で旅館業法の一部規制を緩和した制度です。特区民泊は各都道府県の保健所に申請を出し、認定されると営業が可能となります。
そもそも特区民泊は国家戦略特別区域に指定された地域でのみ実施されている制度であるため、現在は東京都大田区・千葉市・新潟市・北九州市・大阪府・大阪市などに限られます。
簡易宿所(旅館業法)同様に営業上限日数がなく365日営業可能ですが、2泊3日以上といった最低宿泊日数の条件が設けられています。
住専地域での営業が可能(一部地域では条例により制限)となるため、営業の自由度は高い制度になります。該当地域で民泊事業を始める場合には
民泊新法・簡易宿所・特区民泊の比較
民泊新法・簡易宿所・特区民泊それぞれの重要な部分の違いについて解説していきます。
簡易比較表
下記表を別記事より抜粋
| 旅館業法 (簡易宿所) |
国家戦略特区法 (特区民泊に係る部分) |
住宅宿泊事業法 | |
|---|---|---|---|
| 所管省庁 | 厚生労働省 | 内閣府 (厚生労働省) |
国土交通省 厚生労働省 観光庁 |
| 許認可等 | 許可 | 認定 | 届出 |
| 住専地域での営業 | 不可 | 可能 (認定を行う自治体ごとに、制限している場合あり) |
可能 条例により制限されている場合あり |
| 営業日数の制限 | 制限なし | 2泊3日以上の滞在が条件 (下限日数は条例により定めるが、年間営業日数の上限は設けていない) |
年間提供日数180日以内 (条例で実施期間の制限が可能) |
| 宿泊者名簿の作成・保存義務 | あり | あり | あり |
| 玄関帳場の設置義務 (構造基準) |
なし | なし | なし |
| 最低床面積、最低床面積 (3.3㎡/人)の確保 |
最低床面積あり (33㎡。ただし、宿泊者数10人未満の場合は、3.3㎡/人) |
原則25㎡以上/室 | 最低床面積あり (3.3㎡/人) |
| 衛生措置 | 換気、採光、照明、防湿、清潔等の措置 | 換気、採光、照明、防湿、清潔等の措置、使用の開始時に清潔な居室の提供 | 換気、除湿、清潔等の措置、定期的な清掃等 |
| 非常用照明等の安全確保の措置義務 | あり | あり(6泊7日以上の滞在期間の施設の場合は不要) | あり(家主同居で宿泊室の面積が小さい場合は不要) |
| 消防用設備等の設置 | あり | あり | あり(家主同居で宿泊室の面積が小さい場合は不要) |
| 近隣住民とのトラブル防止措置 | 不要 | 必要 (近隣住民への適切な説明、苦情及び問合せに適切に対応するための体制及び周知方法、その連絡先の確保) |
必要 (宿泊者への説明義務、苦情対応の義務) |
| 不在時の管理業者への委託業務 | なし | 規定なし | 規定あり |
参照:https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/overview/minpaku/index.html
管轄省庁と許認可の違い
管轄省庁は表の通り厚生労働省となり、許認可の申請先も基本的に管轄の保健所になります。
許認可内容は、簡易宿所は「許可」、特区民泊「認定」、民泊新法は「届出」となっており、「許可」「認定」「届出」の順で難易度が上がります。
営業日数の違い
簡易宿所・特区民泊では1年間の営業日数がありませんが、民泊新法では180日の上限あります。
一方で、特区民泊では最低宿泊日数の設定があり「2泊3日以上」が必要とされています。
最低床面積の違い
最低床面積の条件にも違いがあり、簡易宿所は合計で33㎡、特区民泊は1室あたり原則25㎡以上、民泊新法は1人あたり3.3㎡となっています。
民泊の種類に困ったら運営代行会社へ相談してみよう
どの種類での民泊運営をすべきか判断がつかない場合は、民泊運営代行会社へ相談することをおすすめします。
国土交通大臣の登録を受けている
民泊運営代行会社が住宅宿泊管理業務を行うために国土交通大臣の登録を受ける必要があります。そのため、民泊運営代行会社は民泊の種類ごとの法律や特徴を熟知しており、所有物件エリアやオーナーの希望に最適な民泊種類の提案が可能です。
家主不在型なら委託は必須
民泊新法の民泊運営において下記いずれかに当てはまる場合は、管理業務を住宅宿泊管理業者へ委託しなければいけません。
- 届出住宅の居室の数が、5を超える場合
- 届出住宅に人を宿泊させる間、不在(※1)となる場合(※2)
(※1)日常生活を営む上で通常行われる行為に要する時間の範囲内の不在は除く
(※2)住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託しなくてもその適切な実施に支障を生ずるおそれがないと認められる場合として以下のいずれをも満たす場合は除く
一気通貫で民泊事業をサポート
民泊運営代行会社は民泊事業の全体計画から、各許可申請、内装・インテリア・備品準備などの開業準備、集客のためのOTA(インターネット旅行代理店)掲載、予約管理、ゲスト対応、清掃・リネンといった民泊運営に必要な業務を一気通貫でサポートしてくれます。
難しい法律が絡み、業務範囲が多岐に渡る民泊事業を、個人で運用するのは非常に難しいことです。手数料を支払ってでも運営代行会社を活用するほうがミスもストレスも少なく民泊事業の展開が可能になります。