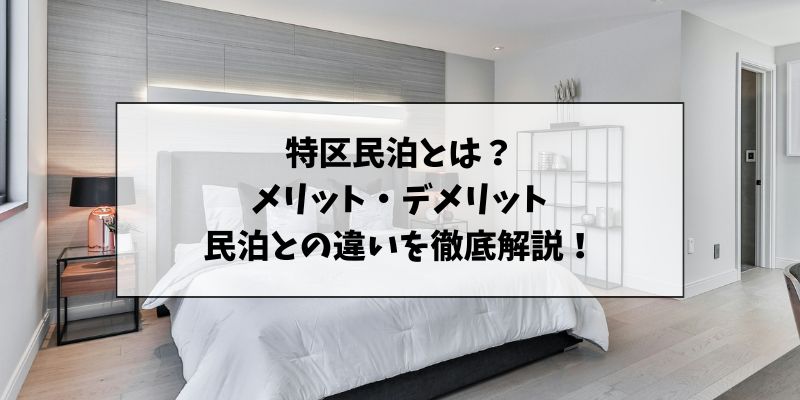コロナで一時は落ち込んだ訪日外国人旅行者も2023年移行の急回復に伴い、空き物件を活用した民泊や賃貸マンションの民泊切り替えなど、民泊ビジネスが注目を集めています。
しかし従来の「民泊新法(住宅宿泊事業法)」では年間営業日数が180日に制限され、高い稼働率を維持しても売上が頭打ちになりがちでした。
そこで注目されるのが、国家戦略特区で認められた「特区民泊」です。今回は概要、通常の民泊との違い、始め方について詳しく解説します。
特区民泊とは
特区民泊は、外国人旅行者の長期滞在を促す目的で旅館業法の一部規制を緩和した制度です。法的には「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業」と呼ばれ、国家戦略特区法第13条に位置づけられています。
特区民泊が可能な地域一覧
特区民泊の対象地域は、東京都大田区・千葉市・新潟市・北九州市・大阪府・大阪市などに限られます。
特に大阪市では2025年の大阪万博があったこともあり、認定数は6,194施設・17,016居室・3,447事業者(うち個人1,237人)となっており、全国でも飛び抜けた実績となっております。全国の認定数が6,542施設・17,809居室・3,741事業者(うち個人 1,348人)ですので、ほとんどが大阪市ということになります。※認定数データは令和7年4月30日時点
利用者は外国人も日本人も対象
特区民泊は、施設自体が「外国人旅客の滞在に適した施設」である必要がありますが、宿泊できるのは外国人に限りません。施設の「利用者」については一切規定がないため、日本人の宿泊も問題ありません。
特区民泊と通常民泊(民泊新法)の違い
特区民泊・民泊新法(住宅宿泊事業法)・旅館業法(簡易宿所営業)の違いは、営業形態や施設構造、申請・手続きなどに違いがあります。比較表でまとめました。
| 特区民泊(国家戦略特区法) | 民泊新法(住宅宿泊事業法) | 旅館業法(簡易宿所) | |
|---|---|---|---|
| 制度目的 | 国家戦略特区で外国人等の滞在を促進 | 空き家活用と観光需要の受け皿 | 宿泊業の一般的な規制枠組み |
| 実施エリア | 特区条例を定めた自治体のみ (例:大田区・大阪市など) |
全国 | 全国 |
| 営業日数上限 | なし | 年間180日まで | なし |
| 最低宿泊日数 | 多くの自治体で2泊3日以上(条例で上乗せ可) | 制限なし | 制限なし |
| 客室面積 | 原則25m2以上 ※壁芯 (滞在者の数を8人未満とする施設では、居室の滞在者1人当たりの床面積(押入れ、床の間は含まない。内寸により測定したもの)が3.3平方メートル以上である場合も可) |
3.3m2×人数 ※内法 | 原則33m2以上 ※内法 (宿泊者の数を10人未満とする場合は、3.3m2×人数でも可) |
| 管理委託の必要性 | 規定なし | 家主居住型であって居室数が6以上 または、家主不在型の場合は管理委託必要 |
規定なし |
| 近隣住民への事前説明 | 実施が必要 | 実施が望ましい | 実施が望ましい |
| 手続き区分 | 認定制 | 届出制 | 許可制 |
| 手数料 | 必要 | 不要 | 必要 |
特区民泊のメリット
特区民泊は運営者にとって大きなメリットがあります。
営業日数無制限で高収益が見込める
民泊新法(住宅宿泊事業法)で定められる180日制限がないため、年間を通じた長期運営が可能です。この営業制限がなく、高収益を見込める点が特区民泊の最大のメリットとも言えます。
民泊事業で収益を最大化させるためには運営可能な180日間を民泊として運営し、残りの期間をマンスリーマンションなどとして運用するなど、別用途で運用が必要であったため、運用難易度が高く、管理コストも高くなる傾向がありました。
特区民泊であれば365日民泊として運営が可能なため、民泊の宿泊者を集めることができれば収益を最大化できます。
許認可ハードルが比較的低い
特区民泊・民泊新法(住宅宿泊事業法)・旅館業法(簡易宿所営業)の許認可はそれぞれ認定制・届出制・許可制となっており、旅館業法(簡易宿所営業)の許可制がもっともハードルが高く、認定制、届出制の順の高さになります。
そのため、民泊事業は参入のしやすさもメリットのひとつと言えます。
特区民泊のデメリット・リスク
一方でデメリットやリスクも存在するため、運営方針に沿って最適な選択が必要です。
対象地域が限定的
特区民泊は国家戦略特区の区域として指定された地域でしか営業ができません。東京都大田区・千葉市・新潟市・北九州市・大阪府・大阪市以外のエリアでは特区民泊の取り組みを行うことはできません。
2泊3日以上の最低宿泊日数がある
特区民泊のエリアでは最低宿泊日数が2泊3日以上といった縛りがあります。そのため、出張利用のビジネス客など需要を取り込むことができず、長期滞在が前提のユーザーを集客しなければいけません。ターゲットユーザーの自由度は他の宿泊施設に比べて落ちます。
近隣住民に対して事前説明の必要がある
特区民泊の対象施設として営業するには、近隣住民に対して事前説明が必要となります。そのため1つ手間が増えます。
しかし、事前説明を行うことは事前理解を深めてもらうことになりますので、メリットにもなりえます。昨今は民泊の営業による近隣住民とのトラブルも増えているため、事前に説明しておくことでトラブルを防止することが可能です。
特区民泊で運営を始めるステップ
ここからは実際に特区民泊を始めるにあたっての手順を解説します。
事前相談
まずは自治体の窓口や保健所、消防署へ事前相談を行い、認定に必要な要件を整理しましょう。
相談に行く際には物件の住所や図面、間取りを持参するとスムーズに相談が行えます。
必要要件の準備
認定に必要な要件がわかったら、その準備を進めていきましょう。主な認定要件は下記になっておりますが、自治体による違いや制度の更新がある場合もあるため、必ず事前相談で整理しておきましょう。
- 一居室の床面積が25㎡以上で施錠可能であること
- 台所、浴室、便所・洗面設備があること
- 寝具、テーブル、椅子、収納家具、調理・清掃に必要な器具などがあること
- 外国語を用いた案内があること
- 滞在期間が2泊3日以上であること
- 建築基準法上「ホテル・旅館」が建築可能な用途地域であること
近隣住民への説明
特区民泊は申請前に近隣住民への説明が必要です。説明方法に関しては自治体の指示に従ってください。説明会の開催が必要なのか、書面だけでの説明で良いのかも自治体によって異なります。
認定申請・申請手数料の納付
近隣住民への説明が完了したら、その結果等を添付して認定申請を行いましょう。
認定申請には手数料が必要で、例えば東京都大田区だと20,500円、大阪市だと21,200円となっています。
認定(認定書交付)
書類審査や現地調査を経て問題がなければ認定となります。認定書が交付されて受領すれば、OTAなどで施設情報を掲載して宿泊者の募集を開始できます。
特区民泊の運営を始めるなら民泊運営代行会社がおすすめ
ここまで特区民泊の制度や手続きについて解説してきましたが、細かい要件定義がある制度で、理解しないといけないことも多いため、初めて運営を開始する人にとってはハードルが高いかもしれません。
特に賃貸借契約で部屋を借りて行う場合には、手続きが長引けば長引くほど賃料負担が大きくのしかかります。
業務効率や知識不足によるトラブル発生のリスクなどの観点から、特区民泊を始める場合には民泊運営代行会社へ相談することをおすすめします。