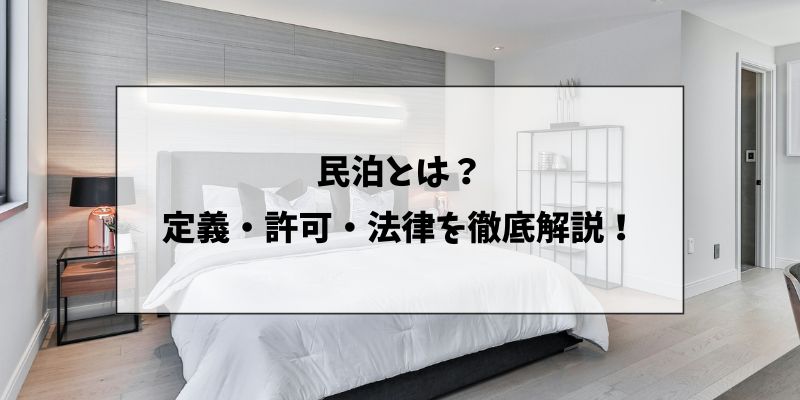民泊について言葉の定義から、適用される法律、運営方法の種類、許認可、申請方法などについて解説します。「民泊とは?」のあらゆる疑問について解決します。
民泊とは?
官公庁が管理する民泊制度ポータルサイト「minpaku」では、民泊を「住宅(戸建住宅やマンションなどの共同住宅等)の全部又は一部を活用して、旅行者等に宿泊サービスを提供することを指して、「民泊」ということが一般的です。」と説明しています。
住宅を宿泊サービスとして提供可能
従来、宿泊施設は旅館業法で管理され、建築基準法上の用途が「ホテル」もしくは「旅館」である必要がありましたが、あらたに住宅宿泊事業法が成立したことで、「住宅」「長家」「共同住宅」「寄宿舎」での宿泊サービスの提供が可能になりました。
副業や新規ビジネスとして人気
法規制が整備されていく背景には、インバウンド需要の増加や宿泊客ニーズの多様化などが挙げられ、観光業界も目まぐるしく変化していっています。
その中で民泊ビジネスは副業や新規ビジネス、新たな投資手法として注目され、専門事業者などが増えたこともあり、人気を集める事業のひとつになっています。
民泊を管理する3つの法律
民泊は、住宅宿泊事業法の届出を行うか、旅館業法(簡易宿所営業)の許可を得るか、特区民泊の認定を得ることで事業をスタートできます。
住宅宿泊事業法・旅館業法(簡易宿所営業)・特区民泊の違い
住宅宿泊事業法・旅館業法(簡易宿所営業)・特区民泊には、主に下記表のような違いがあります。
| 住宅宿泊事業法 (民泊新法) |
旅館業法 (簡易宿所) |
特区民泊 | |
|---|---|---|---|
| 所管省庁 | 国土交通省/厚生労働省/観光庁 | 厚生労働省 | 内閣府(厚生労働省) |
| 許認可等 | 届出 | 許可 | 認定 |
| 住居地域での営業 | 可能(条例により制限されている場合あり) | 不可 | 可能 |
| 営業日数の制限 | 年間提供日数 180日以内(条例で実施期間の制限が可能) | 制限なし | 2泊3日以上の滞在が条件 |
| 宿泊者名簿の作成・保存義務 | あり | あり | あり |
| 玄関帳場の設置義務 | なし | なし | なし |
| 最低床面積、最低床面積の確保 | 最低床面積あり(3.3㎡/人) | 最低床面積あり | 原則25㎡以上/室 |
| 衛生措置 | 換気、除湿、清潔等の措置、定期的な清掃等 | 換気、採光、照明、防湿、清潔等の措置 | 換気、採光、照明、防湿、清潔等の措置、使用の開始時に清潔な居室の提供 |
| 非常用照明等の安全確保の措置義務 | あり(家主同居で宿泊室の面積が小さい場合は不要) | あり | あり(6泊7日以上の滞在期間の施設の場合は不要) |
| 消防用設備等の設置 | あり(家主同居で宿泊室の面積が小さい場合は不要) | あり | あり |
| 近隣住民とのトラブル防止措置 | 必要(宿泊者への説明義務、苦情対応の義務) | 不要 | 必要 |
| 不在時の管理業者への委託義務 | 規定あり | 規定なし | 規定なし |
| 立地規制 | なし(住宅扱い) | あり | 区域計画に定める |
※それぞれ自治体の条例で異なる場合があります。
参考:https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/overview/minpaku/index.html
住宅宿泊事業法の特徴
住宅宿泊事業法では住宅を宿泊サービスとして提供でき、許認可も届出制となっているため、比較的事業を始めやすい法律です。
一方で、年間180日間の営業日数制限があり、事業継続の難易度が上がります。
旅館業法(簡易宿所営業)の特徴
旅館業法(簡易宿所営業)はホテルや旅館と同じ法律になるため、営業可能地域の制限や許認可が許可制となっているなど、営業開始難易度が上がります。
一方で年間営業日数制限がないため、収益性の最大化を狙えます。
特区民泊の特徴
特区民泊の正式名称は「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業」で、外国人観光客の宿泊先不足解消を目的に創設されました。
住宅宿泊事業法と同じように住宅での事業開始が可能であるにも関わらず、年間営業日数制限はありません。
しかし、特区民泊として営業できる地域は国が定めた指定地域のみとなっているため、営業可能対象範囲は少ないです。また、外国人観光客用に設備等を整備する必要性や、2泊3日以上の宿泊を必要とするなどの条件があります。
民泊の営業スタイル
住宅宿泊事業法での営業では、「家主居住型」と「家主不在型」に分かれます。
家主居住型の民泊
家主居住型とは、宿泊者の滞在期間中にオーナーが住民票の住所を置く住宅を民泊として提供し、同じ住宅に滞在していることを指します。日常生活を営む上で通常行われる行為(生活必需品の購入など1時間程度の外出)での不在は認められますが、原則住宅に滞在していなければいけません。
宿泊者の要望やニーズにいち早く対応することができ、料理や体験の提供など付加価値をつけることができます。
家主居住型では、オーナーに住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置(宿泊者への利用説明、衛生管理や近隣住民対応など)が求められます。
家主不在型の民泊
家主不在型とは、オーナーが住宅に滞在していないで運営される民泊を指します。家主不在型の民泊では住宅宿泊管理業者に住宅宿泊管理業務を委託する必要性があります。
また、法人で運営する場合は必ず家主不在型となります。
民泊の健全運営のために必要なこと
民泊サービスの普及によって住居専用地域に観光客が増えたことで、近隣住民とのトラブルなどの社会問題も増加しています。民泊運営者としてはそれらのトラブル等を引き起こさないために健全な運営が求められます。
住居、商業、工業といった異なる目的の土地・建物が混在していると互いに悪影響を及ぼす恐れがあり、そのようなことを回避するために定められたのが「用途地域」です。
用途地域の中の住居専用地域とは、「第一種低層住居専用地域」「第二種低層住居専用地域」「第一種中高層住居専用地域」「第二種中高層住居専用地域」に該当し、住む他の環境が整っている地域になります。
違反行為による罰則
民泊運営は法律に則って営業しなければなりません。もし、違反してしまうと重い罰則が科せられる可能性があります。
例えば、住宅宿泊事業法でも旅館業法でも、届出・許可なく営業を行った場合には「6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこれの併科」があります。
よくある民泊と他の施設との違い
民泊と同じ宿泊施設には民宿やゲストハウス・ホテルがあります。それらとの違いも別の記事にまとめているので参考にしてください。
民泊は一般的にも住宅宿泊事業法か特区民泊で運営されることが多く、民宿・ゲストハウス・ホテルは旅館業法の許可の下で運営されることが多いです。民泊も旅館業法の許可の下で運営されていれば、法律上の取り扱いは同じになります。
民泊と民宿の違い
民宿は家主居住型での運営が多く、地元で採れた野菜や魚などを使った料理やその地ならではのアクティビティ体験ができるなど、地域の良さを体験できる施設が多くあります。
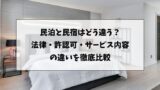
民泊とゲストハウスの違い
ゲストハウスは多数人で共用する宿泊施設であるため、比較的安価な宿泊費用で泊まることができます。また、共用部分で他の宿泊者との交流が生まれることもあります。
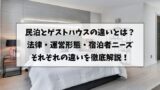
民泊とホテルの違い
ホテルは旅館業法の旅館・ホテル営業になるため、住宅宿泊事業法や旅館業法の簡易宿所営業で運営される民泊とは法律が異なります。